動物も盗聴をすることはご存じだろうか?
盗聴の意味を調べてみると以下のようなものになる。コトバンクより引用。
とう‐ちょうタウチャウ【盗聴】
- 〘 名詞 〙第三者が聞いてはいけない他人の会話・重要な会議の内容などを、当事者にわからないようにこっそりと聞くこと。「盗聴器」
- [初出の実例]「こっそり設けてゐる秘密通信盗聴所の一つだ」(出典:近代科学の驚異(1934)〈寮佐吉〉四)
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例https://kotobank.jp/word/%E7%9B%97%E8%81%B4-103903
しかし、動物のする盗聴とはどんなものなのか?全ての動物に聴覚が有る訳でもなければ、聴覚がある動物が必ずしも泣き声を出せるとは限らない。
第一節 盗聴とは何か?
動物行動学でいう盗聴(eavesdropping)は、本来の受信者以外の個体が他者の信号や行動を横取りし、そこから得た情報を自己の利益に転換する行為を指す。行動生態学の古典的定義では「意図しない受信者による信号利用」だとされ、闘争、採餌、配偶などあらゆる文脈で確認されてきた。
信号が第三者に漏れることには、送信者と本来の受信者の双方にコストを生む場合が多い。送信者は捕食者やライバルを呼び寄せるリスクを背負い、本来の受信者は情報の希少性が下がることで利得を失う。一方で盗聴者にとっては捕食チャンス、配偶機会、安全確保といった直接的なベネフィットがある。結果として通信系は“漏えいを前提とした設計”へと共進化し、周波数のシフト、符号化、時間帯の変更など多様な適応が観察される。
第二節 盗聴の主な種類
同種内での盗聴は、競争相手の位置や社会的地位を推定する手段として働く。たとえばトリニダード産グッピーのオスは、別のオスが求愛している雌を観察すると、その雌への自らの選好を下げる――ライバルとの直接衝突を避ける行動である。
異種間盗聴は、捕食リスクや資源情報を共有するネットワークを形成する。小鳥同士はもちろん、リスやマーモット、チップマンクといった哺乳類が互いの警戒声を聞き取り合う例も報告されている。都市騒音はこの情報網を分断し、異種警報への反応確率を下げることが示された。
捕食者あるいは寄生者が獲物の信号を手がかりにする形態は、盗聴のなかでも最も直接的な利得を伴う。北米の寄生バエ Ormia ochracea は、コオロギのラブソングの振幅と周波数に合わせて鼓膜を共鳴させ、鳴き手の雄に正確に着地して寄生卵を産み付ける。その精度はヒトの聴覚定位を凌ぐほどだ。
逆に被食者が捕食者の発する音を聞き取り回避行動を起こすケースもある。トードフィッシュはイルカのパルス列を感知すると巣穴に籠り、鳴き声を止めることで捕食を避ける。
第三節 具体的事例
コオロギと寄生バエの軍拡競争
ハワイに移入されたコオロギ Teleogryllus oceanicus の一部集団では、雄がまったく鳴かない“サイレント型”が急速に広がった。鳴けば雌を呼べる代わりに O. ochracea に寄生されるリスクが跳ね上がるためだ。サイレント雄は鳴く雄の近くに待機し、雌が接近した瞬間に交尾を狙うという“衛星戦略”で繁殖成功を補う。信号と盗聴者が直接作る選択圧が、数世代で形質頻度を塗り替えた好例といえる。
グッピーの恋愛駆け引き
グッピーの世界ではオス同士の視線が配偶選択を変える。大型のライバルが見ている状況下では、オスは普段好む派手な雌をあえて選ばず、地味な雌にターゲットを移す。盗聴によるリスクを計算し、将来の競争コストを抑える行動だと解釈されている。
小鳥の異種警戒ネットワークと都市ノイズ
北米の混群ではシジュウカラ類やスズメ類が互いの警戒声を“共通語”として利用する。しかしロードノイズを人工的に流す実験では、異種の警戒声に対する反応が著しく鈍り、自種声への依存度が高まった。この結果は、都市化が情報共有ネットワークを狭め、生存率や群れ構造に影響を与える可能性を示している。
カエルとコウモリの捕食ゲーム
中米のフリンジリップドバット Trachops cirrhosus は、トゥンガラガエルの繁殖コールを頼りに狩りを行う。ただし毒をもつヒキガエルの声も混在する環境では、個体発達の過程で音色を学習し、食べられない獲物を選別できるようになる。学習によって盗聴の精度が洗練されることを示す最新研究である。
枝を介した振動通信と捕食リスク
樹上性ヨコバイやカメムシは、枝を振動させる微弱な信号で求愛する。その振動は同じ枝に潜むクモやアリにも届き、待ち伏せ捕食者に位置を暴露してしまう。振動通信ネットワーク全体が“盗聴可能”であることが、信号強度や発信タイミングの進化を制約している。
結語
盗聴は例外的振る舞いではなく、むしろ生態系を貫く情報フローの主役の一つである。送信者・受信者・盗聴者が相互に与える選択圧は、通信の暗号化、タイミング調整、感覚器の鋭敏化といった形で共進化を牽引してきた。都市化や海洋ノイズがこの精妙なネットワークを寸断しつつある現在、盗聴の研究は保全生物学にも重要な示唆を与えている。
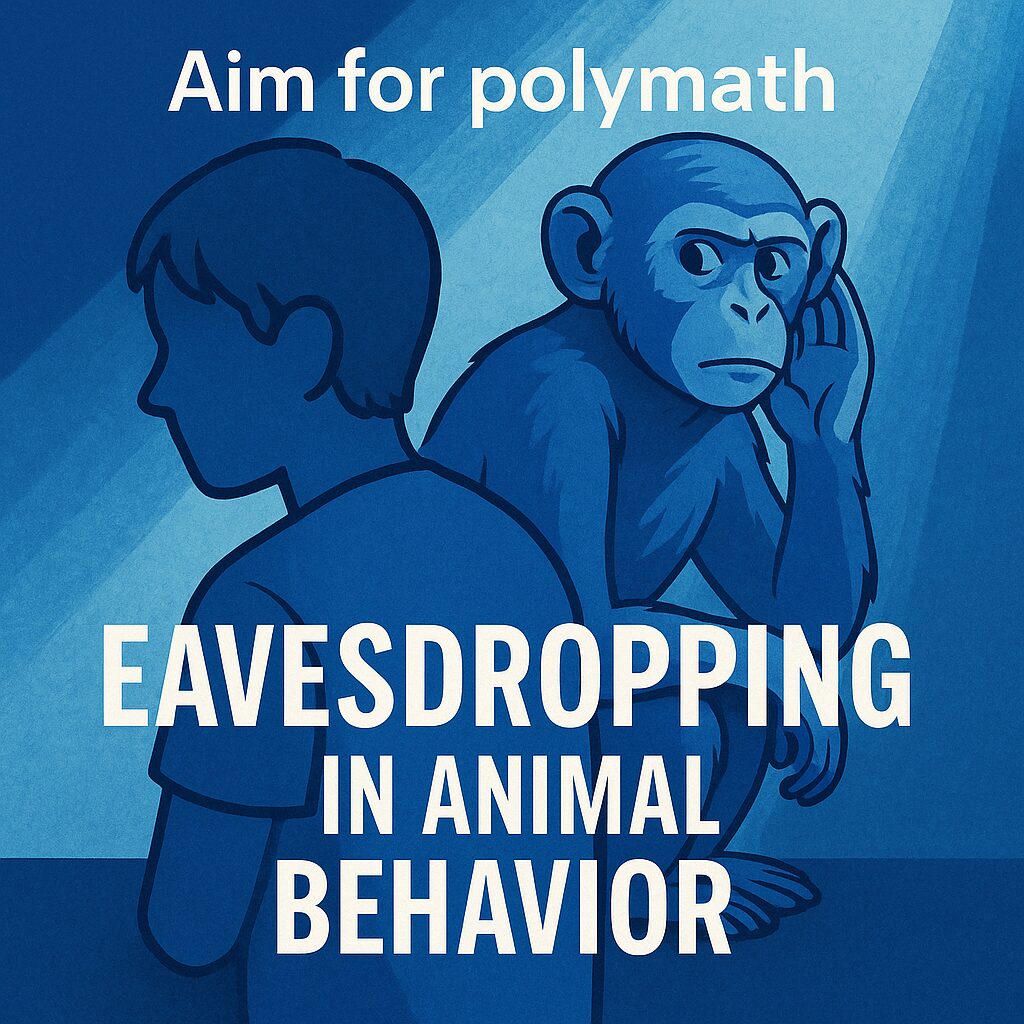


コメント