中国に於る「四害駆除運動」をご存知だろうか?
中国の「四害駆除運動」は、1958年に毛沢東が「スズメを駆除せよ」と人民に号令をかけた政策だ。スズメを大量に駆除した結果、天敵を失ったイナゴが爆発的に増え、作物を食い荒らして大飢饉を招き、数千万人が餓死したと言われている。この壮大な失敗は、「なぜスズメがいたのか」――フェンスの成立理由を無視したことがもたらした悲劇そのものである。
ここで紹介するチェスタントンのフェンスとは、無理解な撤去・排除を戒める教訓である。
起源
G. K. Chestertonは1929年刊行の随筆集『The Thing』で、次のように書いている。
In the matter of reforming things, as distinct from deforming them, there is one plain and simple principle; a principle which will probably be called a paradox. There exists in such a case a certain institution or law; let us say, for the sake of simplicity, a fence or gate erected across a road. The more modern type of reformer goes gaily up to it and says, “I don’t see the use of this; let us clear it away.” To which the more intelligent type of reformer will do well to answer: “If you don’t see the use of it, I certainly won’t let you clear it away. Go away and think. Then, when you can come back and tell me that you do see the use of it, I may allow you to destroy it.
自訳
物事を「改善する」行為と「形骸化させる」行為を区別して考えるならば、一つの明快かつ単純な原理がある。おそらくそれは逆説と呼ばれるだろう。
ある制度や法律、ここでは例として道の中央に設けられた柵や門を想定しよう。
現代的改革者の多くは、躊躇なくそこへ近づき、「これが何の役に立つのか分からない。さっさと取り除こう」と言うだろう。
しかし賢明な改革者はこう答えるべきだ。
「もしその意義が分からないのであれば、取り除くことは許可できない。一度立ち去り、よく考えてこい。そしてその上で『意義が分かった』と言えるようになったとき、初めて取り壊すことを許可しよう。」
出典 https://www.chesterton.org/taking-a-fence-down/
要点
Chesterton’s Fenceの要点はとてもシンプル。
①それがある理由を把握しろ
フェンス(制度・規則)は誰かが何らかの目的で設置したものである。まずその歴史的・社会的文脈を学ぶ必要がある。
②無理解のまま撤廃するな
「なぜ?」が解けなければ、思わぬ落とし穴が待っている可能性が高い。
③それを設置した奴の意図を理解しろ
設置者の意図を理解し、それが現在も有用か検証したうえで、はじめて変更を検討する。
具体例
具体例①中国の四害駆除運動
概要
1958年、毛沢東は大躍進政策の一環として「四害(ハエ・蚊・ネズミ・スズメ)駆除運動」を全国規模で開始した 。
スズメは農作物の種子を食べる害鳥とみなされ、多くの餌となる昆虫も駆除対象とされた。
どう失敗した?
組織的にスズメの駆除を進めた結果、天敵のいないイナゴが大量発生し、農作物を食い荒らした。当時の農業学者や村民は、スズメの生態系に於る役割を理解していなかったのだ。
そして、1959年以降農業生産が落ち込み、飢饉により1500万~3600万人が死んだとされる。四害駆除は、この飢饉の主因とされる。
チェスタントンのフェンスから見る
スズメというフェンスの役割を理解しないまま取り除いた結果、飢饉を招いた。
結果論にはなってしまうが、スズメが無意味な存在や害鳥に見えても、なぜスズメがそこにいるのかを考えるべきだった。
参考資料
The Four Pests Campaign: Objectives, Execution, Failure, And Consequences – WorldAtlas
具体例②スタートアップの菓子代削減
概要
Steve Blank 氏のブログ記事によると、或るスタートアップが新任CFOの指示で無料のソーダとスナックを有料化したところ、最も優秀で経験豊富なエンジニアが次々と退職し始めたと報告されている。Steve Blank The Elves Leave Middle Earth – Sodas Are No Longer Free
無料のスナックやソーダがなくなることは、管理職対従業員という文化的断絶の兆候であり、それを契機に優秀な人材が「いざというとき離脱すべき企業」と判断するのだと、Hacker Newsのコメントで指摘されている。Getting rid of free office snacks doesn’t come cheap | Hacker News
この記事の調査では、多くの企業リーダーが「無料スナックは従業員ニーズの一環」と認識している一方で、コスト削減を優先し短絡的に廃止するケースが増えていると報告されている。Title Unavailable | Site Unreachable
スナック制度の価値
スナック制度は単なる「おやつ」ではなく、従業員のエンゲージメントや定着率向上に寄与する重要な施策であることが複数の研究で示されている journals.sagepub.com。さらに、以下の調査によれば、「無料ランチやスナックは従業員満足度を最大67%向上させる」というデータもあり、これをコストとしてのみ捉えるのは誤りである fooda.com。
どうすればよかったのか?
まずスナック制度を廃止する前に、スナック制度の目的(社員満足、創造性促進、採用競争力強化)を定量・定性で分析し、社内アンケートやログデータを活用して評価すべきでした hungerhub.com。
他にも、完全廃止ではなく、まず「種類削減」「利用回数制限」「従業員負担導入」といった段階的変更を A/B テストで試行し、影響を測定する方法が望ましかった councils.forbes.com。
さらに、ワークショップやタウンホールミーティングで意見収集を行い、制度改廃の意図を説明したうえで代替案を共創すると、反発を抑えられた可能性がある forbes.com。
この事例をチェスタントンのフェンスから見る
この事例の失敗の原因は、スナック制度というフェンスが従業員を支える役割を果たしていた点を事前に調査せず撤去してしまったことだ。
その結果、企業文化の根幹を揺るがし、従業員離脱という予期せぬ落とし穴”に陥った。
フェンスの撤去前に、フェンスの果たす役割を調べ、理解し、その上で撤去するかどうかの判断を下すべきだった。
「チェスタントンのフェンス」という思考法の使い方
Step①フェンスの識別
撤去したいものを認識する
Step②フェンスがそこにある理由を考える
このフェンスは「誰が」「いつ」「なんのために」設置したのだろうか?フェンスを撤去する前に、関係者への聞き込みや、関係書類や当時の背景を調べよう。
Steps③役割の理解と価値の評価
調査に基づき、フェンスがどんな役割を果たすもので、実際に今どのような役割を果たしているかを理解する。
Step④実行
フェンスを完全撤去するか、段階的な機能縮小か、現状維持か、どういう行動を取るかを決める。
Step⑤
フェンスに対して何らかの行動を取った場合、行動後に期待した改善が実現しているか、予期せぬ副作用が起きていないかを調査する。
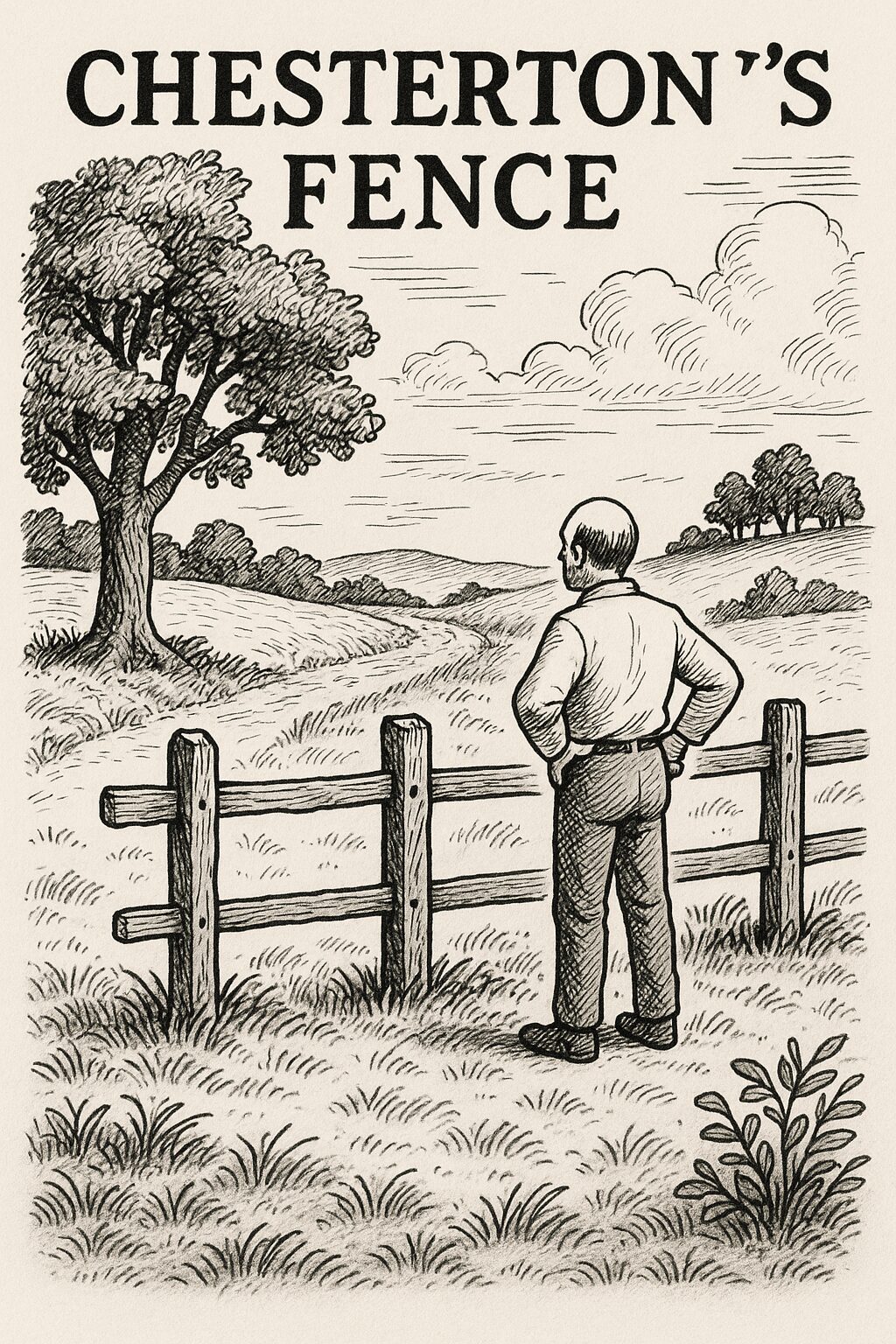
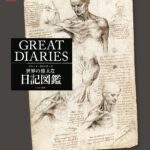
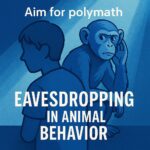
コメント