伊藤計劃作
<harmony/>ハーモニー
ハヤカワ文庫、2010
あらすじ
「大災禍」と呼ばれる世界規模の混沌から復興した世界。かつて起きた「大災禍」の反動で、世界は極端な健康志向と社会の調和を重んじた、超高度医療社会へと移行していた。そんな優しさと慈愛に満ちたまがい物の世界に、立ち向かう術を日々考えている少女がいた。
少女の名前は御冷ミァハ。世界への抵抗を示すため、彼女は、自らのカリスマ性に惹かれた二人の少女とともに、ある日自殺を果たす。
13年後、霧慧トァンは優しすぎる日本社会を嫌い、戦場の平和維持活動の最前線にいた。霧慧トァンは、かつての自殺事件で生き残った少女。
平和に慣れ過ぎた世界に対して、ある犯行グループが数千人規模の命を奪う事件を起こす。犯行グループからの世界に向けて出された「宣言」によって、世界は再び恐怖へと叩き落される。霧慧トァンは、その宣言から、死んだはずの御冷ミァハの息遣いを感じ取る。トァンは、かつてともに死のうとしたミァハの存在を確かめるため立ち上がる。
(公式サイトhttps://project-itoh.com/harmony/から引用)

(公式サイトhttps://project-itoh.com/harmony/から引用)
左の白い女性が御冷ミァハ。世界を切り裂くナイフのような女。
右の赤い女性が霧慧トァン。
「ハーモニー」の位置づけ
この「大災禍」(ザメイルストローム)と社会の混乱は、伊藤計劃の作品「虐殺器官」の次回作にあたる。
―――『虐殺器官』の世界観を突き詰めていくと、『ハーモニー』の中に出てくる〈大災禍〉的なことが起こるわけですよね。 それ以後の世界というものを今回は描いている。
伊藤 そうですね。ある種の続篇だと思います。
p369 ハーモニー 伊藤計劃インタビュー
どちらを先に読んでも十分に面白いが、できるなら先に「虐殺器官」を読むべきである。そうすれば、ハーモニーという作品の剛健な老人たちが恐れる脅威を、深く理解できる。
虐殺器官を混沌の極致とすれば、ハーモニーは調和の極致だ。ハーモニーの世界ではずっと健康でいれて、長生きできて、傷つくことがない。これら作品を連続で読めば、両極端を体験できる。
伊藤計劃は、「虐殺器官」を書いた後に、「ハーモニー」を書いた。この作品の出発点は「虐殺器官」を書いた後にある。
伊藤 『虐殺器官』では「虐殺の言語」っていうものを描いたわけですけれども。ならば人間が生得的に持っている、そういう器官があったらどうなんだろう。じゃあそれを抑えるものがあったらどうだろう、絶対的に平和な世界が描けたらそれは一体どんなものなのか、ていうのが最初の発想ですね。平和な世界のストレスを描くという。僕自身が病院にずっと入っていますので、どうしても医療と人間っていう観点から考えるようになっていて、人間をコントロールする人工性とかライフスタイルとかの、ある種のコードを書いていくっていう。そういうのがやれたらっていうのが出発点です。
p368 ハーモニー伊藤計劃インタビュー
不健康は罪
不健康は、見た目に出る。
肌荒れというのは要するに、生命社会の嗜みであるそれらのうち、どれか一つ以上をサボっているという証。調和を乱す者の証。生命社会とは男女問わず不摂生を許さないライフスタイルのことでもある。不摂生は必ず肉体に刻まれるのだ。
肌荒れはセルフコントロールの喪失。
目の下のくまは社会的リソース意識の欠如。
p82 ハーモニー
我々の生きる社会では、肌荒れも睡眠不足や運動不足も暴飲暴食も、個人の問題だ。しかし、健康と調和を重んじるハーモニーの社会では、それらは罪となる。喪失、欠如、欠陥、不足、欠落…あるべき健康な状態から外れたら、その状態は全て、不完全と看做され、是正されるべき対象になる。
自由がない。自分にデメリットのある選択をする自由と、不完全な状態を改善しない自由がない。失敗する自由と傷つく自由は放棄してもいいものだろうか?その先に、人の幸せはあるのだろうか?
パターナリズム(父権主義)の行きつく先に幸せはあるのだろうか?
「慈母によるファシズム」
p84 ハーモニー
あなたの為だから、という理由で強い者は弱い者に干渉する事を、パターナリズム(父権主義)という。
シートベルトをしろ、SNSに個人情報を上げるな、などなど…
これらは、自分で自分が被るリスクを選び取る自由が侵害されている、とも言える。シートベルトをせずに交通事故に遭えば、フロントガラスを体が突き破り、身体は車道に転がり、他の車に轢かれるだろう。
SNSに安易に個人情報を晒すと、将来就職に支障がでたり、家を特定されて日常生活が危うくなるかもしれない。
ハーモニーで提示される世界は、パターナリズムの極致である。その社会では、潜在的な傷つくリスクが最大限に排除されている。そこでは、リスクを選び、リスクを被る自由が制限されている。虐殺器官の世界と同じように、傷つけないから成長できない。教訓を自分のものとして身につけれない。
「虐殺器官」と「ハーモニー」の共通点
虐殺器官とハーモニーは似ている。人が傷つくことができない社会になっている。人を傷つける潜在的な原因が事前に排除されている。
虐殺器官では、主人公の脳に感情を制御するパッチがあって、人を殺して悲しんだり後悔したりできない。だから、傷つくことができない。
ハーモニーでも、人が傷つくのを事前に警告され、人を傷つけそうなものが排除されている社会システムがある。
傷つけないとは、成長できない、教訓を得ることができないことを意味する。痛みを伴わない教訓は直ぐに忘れ去られる。人が傷つくことのできない社会は、人が反省し改善できない社会だ。
主観的な痛みを知らない人は、誰かが「痛い」と言っていても、その痛みを想像できない。痛みは私秘的で、共有できないから。
これは、身体的な感覚に留まらず、嘗て疫病で何十万人と人が死んだ惨劇や、世界大戦で起きた被害と、災害で起きた惨害も想像できないということになる。となると、書物などで記録したかつての教訓を生かせない。昔、なにがあったから、こんなルールができて、それを守らないといけないのかという背景情報と経緯―――すなわち歴史である―――を知らないなら、法律や社会システムは有効性を失う。何故なら、歴史なしには、それらの存在意義が忘れ去られるから。意義や意味の分からないものは、遠からず忘れ去られ、等閑視される。
鼬ごっこ
生活の中で蓄積された健康保護アプリケーションの一部であるプロファイリングシートは、いわばもうひとりのわたし。
わたしが嫌悪するものすべてを引き受けるわたし自身。
それは生府のサーバの中にあって、日々の生活の中からわたしの好みと嫌いなものと倫理的傾向を検出し、文学とか絵画とかがわたしを傷つけないように日々全力でわたしの生活を監視している。これから読もうとしている小説やらエッセイやらの中に、セラピー履歴に照らして過去のトラウマに抵触する描写や部分があれば、勝手にフィルタリングしてしまうか事前警告するかしてくれる。この芸術作品はあなたの心的外傷に触れる可能性があります、この小説は一般的倫理検証項目四〇八九六A(ヘルス&クリア生府倫理評議会二〇四九年十二月四日策定)に抵触する恐れがあります、と。
p84~85 ハーモニー
もしも我々の住む社会で、このように毎度毎度警告が出たらどうなるだろう?
皆が大好きな広告ブロッカーよろしく、警告ブロッカーが開発されて、アプリのダウンロードランキングで上位ランキングを総なめするのだろうか?
当然、全員が警告をブロックすることになれば、警告の意味がなくなるから、個々人に紐付けられたプロファイリングシートの状態を鑑みて、警告は強制的に為されるだろう。しかし、自分のプロファイリングシートを改竄し、健康状態を偽る技術が出てきて、霧慧トァンのように実際にそれらを偽る人も出てくるだろう。現実のセキュリティ問題みたいに、鼬ごっこだ。
しかし、ハーモニーに於る世界で、霧慧トァンのような人物は圧倒的に少数派だ。これの原因は、アメリカを滅ぼしたザメイルストロームで感じた恐怖だ。ともすれば人はまた殺し合うのではないかという疑念が、常にこの社会の根底にある。
だが、疑念と恐怖だけでなく、社会システム自体が人々に「社会に於る当たり前」を強要するようになっている。
みんながみんなを人質にとる社会
「他者を信じなければならないという強迫観念こそが、この社会を支えていた。互いが互いを少しずつ人質にとるとはそういうことだ。老いと事故以外では死なない人間たちが、絶えず個人情報を晒し、生府のディスカッションや倫理セッションには必ず参加して、然るべき専門家の助言を受けながら合議で物事を決める。」
p193 ハーモニー
これってルソーが言ってたような社会契約の行きつく終着点だ。皆が自分自身を皆に人質として捧げているなら、それは誰も誰にも捧げていないのと一緒だ。
Ces clauses, bien entendues, se réduisent toutes à une seule, savoir, l’aliénation totale de chaque associé avec tous ses droits à toute la communauté : car, premièrement, chacun se donnant tout entier, la condition est égale pour tous; et la condition étant égale pour tous, nul n’a intérêt de la rendre onéreuse aux autres. p26~27 フランス語で読む哲学22選
自訳
なぜなら、第一に、各人が自分を完全に差し出すことで条件は全員に平等となり、その条件が全員に平等である以上、それを他者にとって重荷にする | 負担となるようにするのが得策である者はいないからである。
「他者とは、他人とは本来的に予測のつかない気持ちの悪いものなのだ」
p193 ハーモニー
これはレヴィナスの「全体性と無限」の、他者観じゃないか?と読んでいて感じた。伊藤計劃は、レヴィナスを読んでいたのだろうか?ドゥルーズは読んでいたらしいので、もしかしたらレヴィナスも読んでいたかもしれない。
伊藤 社会と自己の対立みたいなのは昔からあるテーマではあるんですけど、最近ゼロ年代の話とかでよく出てくる「小さい共同体」とか、そういう話がありますけど、共同体を論じる以前に、動物としての人間っていう部分が議論からすっぽり抜けているような気がするっていうか。ドゥルーズとかはデータベース化して管理する世界っていうのを『記号と事件』かなにかで書いてましたけど、人間が動物である部分と社会的な存在である部分の折り合いをどうやってつけるのかっていうことに対して、あまり議論がないのが不思議な気がしていて。そこを書いてみたいなっていうのはありましたね。共同体を立ち上げる前に、まず 「人間」を把握するのが先じゃないか、と。
p371 ハーモニー 伊藤計劃インタビュー
私に自由にならないものとしての他者
レヴィナスによると、私という一人称は、自分とは違うものを把握してそれを自分のものにする。「私」によって把握されたものは、もう既に観念として「私」の中にある。そもそも理解できないようなものは、自分にとって理解できる形に整形されてからでしか、記憶に残れない。
このように、「私」の生は、自分とは違うものを自分と同化させることで自分を完結した存在にしようとする。つまり、自分が把握した対象を把握する前は、把握した後に比べて欠落があって、不完全だった。その欠けを何かを把握することで埋めて完全になろうとする。「完結した存在になろうとする」とは欠けを補ってより充実した存在になろうとすること。
※この世の全てを把握して本当の自分だけで完結した存在になることは不可能だが、そうなろうとすることは可能だ。
この枠組みの中だけなら、つまり脳内での思考の中では、自分の自由にならないものはひとつもない。
だが、他人は「私」が予想できない言動と行動をする。他者は簡単にあなたの常識や普通やこういう風になるだろう・動くだろうという予想を超えてしまう。他者は自分に対して命令してくることもある。それは、その他者に自分以外にも人格があると思わせる。
レヴィナスは自分の中で何でも自由になる領域を全体性と呼び、自分の用意する枠組みを超えて行ってしまう他者を無限と呼んだ。
(c.f. p221~230 入門・倫理学の歴史 24人の思想家 2016/3/10柘植 尚則 (著, 編集), 西村 洋平 (著), 武富 香織 (著), & 13 その他)
生きることの分業化
p199
人間が身体の管理を「外注」に出した、これが結果だ。
WatchMeを使って自分の身体を他人任せにした結果、人は外部のシステムなくしてはその身体を維持することすらかなわず、こうしてそこにつけこまれる状況を招いた。人は生きることに関する様々な事柄を分業化してきた。
皆が皆に依存する社会システムを確立できれば、皆がリスクを取れなくなる。なぜなら、全員が自分を人質に出しているから。安定性に優れるだろうが、そのデメリットは?==このハーモニーの世界は何が問題なの==?個人から見たら確かに退屈に感じる人も、退屈な場面をあるかも。窮屈に感じるかも。しかし、その分、弱く馬鹿な大勢の人間が幸せになれている。大勢の人が、自分より賢く正しい者に決めてもらいたい。決めてもらって意思決定という労苦を省き、さらに自分で決めていたら絶対辿り着けなかった結果にたどり着けるなら、その世界は上手く回っているのではないか?
攻殻機動隊で、草薙素子が、人は脳を外部化する前にもう一度よく考えるべきだった、みたいなことを言っていた。人はいつでも、技術の便利さに飛びつく前に、そのデメリットと「すべきかどうか」について検討しなければならない。
ひとりで色んな事を学ぶより、一つことに絞って、分業化した方が、社会は発展する。分業するべきなのは、何の何処迄のレベルなのかをしっかりと考えるべきだろう。生きるのに必須なことすら分業化していいのか?と。現実に、自分の健康管理や意思決定(もうこれは「GPT4に任せる」という選択肢が現実にあるので、もう意思決定の分業化は現実で始まっている。)
意識
「あなたは思ったのね。この世界に人々がなじめず死んでいくなら―――」
「そ、人間であることをやめたほうがいい」
p343
もしも意識が生存や繁殖に優位でなくなったら、人類は意識を捨てるべきだろうか?作中では、「わたしはわたしである」という鏡写しの意識こそが、人間の尊厳だっていう主流派と、意識を放棄してハーモニーを望む少数派がいた。
その少数派に属する霧慧トァンは意識のなくなったハーモニーを恍惚だったと述べたが、意識の消滅と死は何が違うのだろう?生物学的には、意識が有ろうとなかろうと、ハーモニーの状態にある人間は生きている。現実に於る虫や動物にも意識があるのかどうか、まだ結論は出ていないようだ。しかし、それらの生物は意識があろうとなかろうと生きている。細胞や微生物も同じく、生きている。では、意識にとって生(生きているということ)とはどういう関係にあるのか?また、生にとって意識とはどういう関係にあるのだろうか?
哲学的ゾンビ、という思考実験がある。哲学的ゾンビとは、内面的な意識を持たないこと以外は普通の人間と同じ存在のこと。或いはその思考実験のことだ。
客観的には、意識があるかなんて判別がつかない。普通の人間と哲学的ゾンビの違いは外から眺めるだけでは分からない。「痛い!!!」とか「好きです」とか、言葉に伴う表情は至って正常だ。しかし、言葉にも行動にも意識が伴っていない。意識がないから。
「あいつに意識はあるのだろうか?」という問いは、その問を投げかける対象が石ころであれ、人で有れ、蠅であれ、確かめるのは不可能に近い。
意識があろうとなかろうと、人の思考と行動が不変なら、意識には何の意味もないのかもしれない。だが、人が生存する上で、意識は何らかの優位を齎す形質だったからこそ、意識という不可思議なものが人にあるのではないか?
霧慧トァンは、意識を糖尿病のようなものだと言っていた。糖尿病は今でこそ根治されるべき病気だ。糖尿病時の血液は氷点が0度以下になる。その為、極寒の環境に於ては、糖尿病の人間の方が生存に有利だ。糖尿病により血管と臓器がボロボロになって数年も生きれないかもしれないが、極寒の環境では、皆明日死ぬかもしれない。死ぬまでに子孫さえ遺せれば遺伝子にとっては万々歳という訳だ。
だが、今や糖尿病は治されるべき病気である。ただ生存に有利だったからという理由で、その場鎬の継ぎ接ぎで意識や糖尿病が人にあるのなら、孰れ意識も治療されるべき形質と看做されるのか?
映画とその主題歌
「虐殺器官」と「ハーモニー」はともに映画化されている。
上記二つの動画が、「虐殺器官」の映画PVとその主題歌。
「ハーモニー」の主題歌もEGOISTが担当している。最後の動画はおまけ。筆者のお気に入りなので貼っておいた。
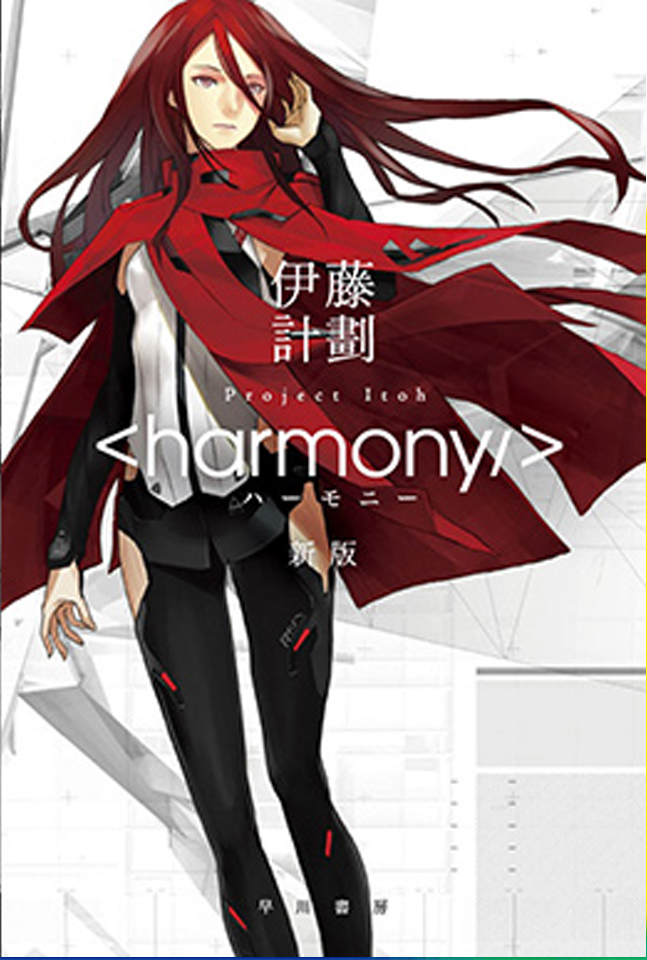

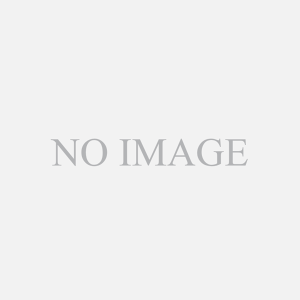
コメント