SF小説の価値は、その発想にある。テッド・チャンの短編『息吹』は、この命題を完璧に体現する作品である。
物語の形式は、思考能力を持った或る知的存在が「銅板」に残した記録、という体裁をとる。この時点で、我々読者は既にこの未知の世界の探検家あるいは考古学者としての役割を与えられる。
肺を交換する文化と、世界の「ズレ」
彼らの世界は、我々とは根本的に異なる。彼らは金属の体ち、毎日の「肺」の交換によって生命を維持している。それは数百年の寿命を可能にする日常的な行為だ。
作中では、ガソリンスタンド兼サロンのような場所で、彼らが集い、お喋りをしながら肺を交換する文化が描かれている。
彼らの体の構造は、その大部分が解明されていた。しかし、唯一「脳」の構造だけは、長らく謎に包まれていたのである。
物語は、ある奇妙な「ズレ」から動き出す。 彼らの文化には、詩を暗証する職業が存在し、その詩は正確に「1時間」で暗唱し終わるはずだった。しかし、ある時から「時計が1時間を告げた後も、暗唱が終わらない」という現象が各地で報告され始めた。
時計の仕組みは、振り子時計や水銀を使ったものなど、場所によって異なる。だが、その仕組みの違いに関わらず、同様の事例が報告された。
この日常に忍び寄る些細(ささい)な違和感。この詩的で静かな「ズレ」が、最終的に宇宙の終焉という壮大すぎる真実へと繋がっていく構成は、見事である。
自らの脳を分解する「狂気」の探求心
この事態を解明するため、銅板の筆者である主人公は、或る決断を下す。 自らの思考能力を司る部分(=脳)を分解し、その仕組みを解明しようと試みる。
彼は部屋の四方にプリズムを配置し、顕微鏡のような拡大装置を通して、自分の後頭部が目の前に映るように展望鏡をセッティングする。さらに、極小の作業ができる作動ロッド群を使う。展望強の先には、上下左右に動かすことのできる台に載せた双眼顕微鏡が装着されている。この装置を使って主人公は後頭部を自ら分解し始める。
これは、自らの意識を保ったまま、その意識の源泉である脳を「手術」する行為である。主人公も例に漏れず、毎日肺を交換しなければならない。彼らの文化では、この手術は狂ったものと見られる為、協力を仰ぐことはできない。更に、手術中は身動きができない。その為、主人公は満杯にした12個の肺を部屋に持ち込み、多岐管に接続した後、自分が座る席の前にある作業テーブルの下に肺を据え付け、胸の内側にある気管支の先端部に給気管を直付けにした。これによって、6日分の空気供給が確保できた。
「記憶」の物理的実体と「命」のエネルギー源
脳を分解していくと、稠密なパーツ群が現れる。筆者はパーツを一つずつ外し、機能を維持するために管を差し替えていく。
そして、脳の中心部に到達する。
そこにあったのは、無数の極小の金箔の欠片が蝶番のように備わった機構だった。空気の流れがこの金片を動かし、その相対的な位置こそが記憶を保持する仕組みであった。
ここで我々は哲学的な問いに直面する。心や記憶とは、単なる物理的な配置に過ぎないのか。もしそうなら、「私」という存在とは一体何なのか。本作は、その問いを冷徹なメカニズムとして提示する。
さらに、彼は世界の根本的なエネルギー源をも発見する。 彼らの文化では「空気」そのものが命の源だと考えていた。だが、実際はそうではなかった。
彼らの思考と体を動かしていたのは、空気そのものではなく、「気圧差」によって流れる空気の「本流」だったのである。
エントロピーの寓話と、不可逆な「死」
この発見から、筆者は恐ろしい仮説にたどり着く。
詩の暗唱と1時間の「ズレ」が生じた理由。それは、脳に流れる空気の本流が、ほんの少し「遅く」なったからではないか。
つまり、彼らの世界を覆う空は無限ではなく、何処かに限界がある。そして、世界全体の「気圧差」が徐々に均一になりつつあるのだ。
気圧差が完全に均等になった時、空気の流れは止まり、彼らの思考は完全に停止する。 それは「死」である。
さらに絶望的なのは、一度思考が停止すれば、記憶を保持していた金片の位置はすべて「ゼロ」に戻ってしまうことだ。たとえその後、何らかの方法で再び空気を流したとしても、そこにはもう何の記憶も残っていない。
この設定は、我々の宇宙における「エントロピー増大の法則(熱的死)」の寓話である。エネルギーは常に一方通行で拡散し、やがて宇宙全体が均一で静的な「死」を迎える。この冷徹な物理法則が、気圧差という詩的な物語に昇華されている。
滅びへの「態度」と、遺された言葉
この気圧差の減少は、不可逆である。銅板の筆者は、それに抗う装置を作ろうとしても、気圧を軽くする(エネルギーを生み出す)分よりも多くの空気(エネルギー)を消費してしまい、気圧の収支は必ず赤字になると結論づける。
抵抗は、無意味なのだ。
世界の終わりが確定し、数世紀かけて自らの思考が少しずつ鈍くなっていく。その中で、筆者は何を選んだか。 ただ事実を受け入れ、自分たちが見出した知の記録を、後の誰かのために「銅板」に刻むことを選んだ。
筆者は、この宇宙以外にも別の宇宙が存在する可能性を夢想する。いつか、世界の端にあるクロムの壁を、外から探検家が貫いてくれるのではないか、と。
『息吹』が我々に問いかけること
この物語のタイトル『息吹(Exhalation)』は、彼らの生命線である「空気の流れ」を指すと同時に、滅びゆく主人公が最後の力を振り絞って銅板に刻んだ「言葉」そのもの、彼らの最後の「ため息」をも象徴しているのだろう。
銅板の記録は、こう締めくくられる。
探検家よ、あなたがこれを読んでいるいま、私はとうの昔に死んでいるが、それでもわたしは、あなたに別れの言葉を贈ろう。存在するという奇跡についてじっくり考え、自分にそれができることを喜びたまえ。わたしにはそう伝える権利があると思う。なぜなら、いまこの言葉を刻みながら、わたし自身がおなじことをしているからだ。
この最後のメッセージは、作中の「別宇宙の探検家」に向けられたものであると同時に、時空を超え、ページをめくっている「我々読者」の胸に突き刺さる。
我々もまた、有限の生と、いつか熱的死を迎える宇宙の中で、「存在するという奇跡」を享受している。思考できるという奇跡を、どう使うべきか。
『息吹』は、静かに、だが鋭く、我々自身の存在の重さを問うてくる傑作である。


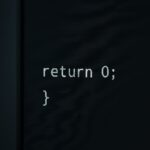
コメント